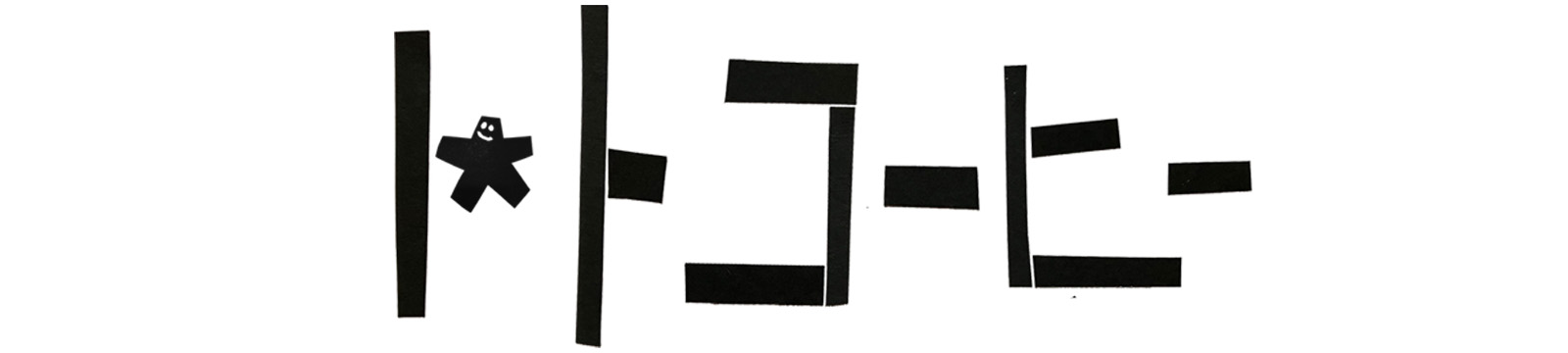別れはいつも突然のようにやってきて、私はその手を離すことをいつもためらってしまう。
あなたが私の世界で不在になるということがどんなことなのか、今はまだよく分かっていない。
靴下が3回はくと穴が開いてしまう。
そういった仕事をしていた。重たい荷物を運ぶので、どうしても足を踏ん張ってしまう。
靴下には決まって小指の外側部分に穴が出来た。その穴以外はまだまだ使える状態だったけど、私は穴が出来るとすぐに捨てた。
名前を出せば誰もが知っている、そんな有名な会社へ入ってまわりは喜んだ。
しかし、最高の品質の製品を製造する現場では、常に完璧な仕事が求められた。
ただでさえ、今までとは違う業種で困惑している上に、何もかもが計画立てられた会社の中では、私という人間のいい加減さや不真面目さを隠す場所などどこにもなかった。
そんな私を真正面から見るたびに、私はひどくみじめな気持ちになった。
靴下を捨てるたびに、私の人生も使い捨てられるように終わっていく‥そんな予感が渦巻いていたように思う。
毎日、夜明けと共に家を出て、同じ仕事をまっくらになるまで汗だくになってする。仕事を終えると誰とも口をきけないくらいヘトヘトになって家に帰る。
その繰り返しは、言葉にすると恐ろしいほど単調で、つまらないことに聞こえるかもしれない。
しかし、私はその単調なリズムに乗って、毎日違う歌を聴いていた。
それは工場の中を行き交う車両同士のあいさつであったり、部品を組み立てる沢山の手のおしゃべりであったり、大きな機械が発するびっくりするような元気な声だった。
決して耳ざわりの良いものではなかったけれど、彼らは仕事に慣れずに失敗ばかりする私を、責める訳でも同情する訳でもなく、ただそばにいてくれた。
上手く説明することは出来ないけど、それが私の仕事だけではなくて、もっと色んなところを支えてくれた。
私は相変わらず同じ仕事で同じ失敗を繰り返していたけど、失敗しても失敗してもあなたが私を見捨てず、手を差し伸べてくれていることにやっと気づいた。
それからだったと思う、私が靴下を捨てなくなったのは。
相変わらず靴下には穴が開いたが、私は疲れ切った体で靴下へ針を入れて穴を塞いだ。
補強した靴下はゴロゴロして履き心地は悪かったけれど、私の仕事の良き理解者となってくれた。
色付いた葉っぱが慣れ親しんだ木の枝を離れ、風に乗って飛んでいく。
別れの予感はいつも明確で、次の道も示されている。
だから彼らは怖れも不安もなく、ひょうひょうと旅立っていく。
自ら答えを出すことにひどく消極的な私は、その美しい景色を、指をくわえて見過ごしていくだけだった。
「仕事を辞める」
ようやく、自らの選択を胸に抱えて出勤した私に、あなたは初めて声をかけてくれた。
「祈ってほしい」
あなたの役に立てることなど何もないと思っていたから、私は耳を疑った。
しかし、あなたに必要とされたことがただ嬉しくて、その日から、晴れた日も雨の日も長い夜の間もひたすら祈った。
苦しい時には広い屋根のような木陰で休息を与えてくれて、ひもじい時は実った恵みを惜しみなく分け与えてくれた。
誰よりも空に近くて、誰よりも遠くを見渡せる。
あなたは皆に愛されているおおきな木だった。
祈りながら仕事をしていると、ひょっとしたらずっとあなたと一緒に過ごすことができるような気がしてきた。その気持ちは、日に日に増して、離れたくないという欲求へと変わっていった。
だけど、あなたは「ありがとう」と言うと、私の期待を取り上げ、おおきな手を離して私の背中を押してくれた。
今はまだ、あなたのいない景色の中を歩いていくことがとても困難のように感じる。
耳に馴染んだあのリズムと歌を忘れる日は、果たして来るのだろうか、とも思う。
孤独を受け入れたつもりでいたのに、いつの間にか私の周りは、いとおしいものであふれてしまっていた。
誰もいない、まっくらやみ
つぎはぎだらけの靴下に足を入れる
空を見上げて祈り、深く呼吸をする
ありがとう 私は行きます